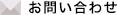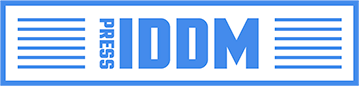日本IDDMネットワークでは、毎日のインスリン補充が欠かせない患者とその家族一人ひとりが希望をもって生きられる社会の実現を目指し、以下の政策要望を行っています。
成人の患者支援実現について
現状
要望内容
- 「指定難病」として「1型糖尿病」を追加
- 当面の対応策として1型糖尿病患者への医療費助成を25歳まで引き上げ
進捗状況と今後の対応
- 「指定難病」への認定
1型糖尿病の指定難病認定については、厚生労働省の第28回~第30回指定難病検討委員会(2019年1月まで)で検討されたが、1型糖尿病は全ての要件を満たしていないということで見送りになっている。それ以降は1型糖尿病については検討対象にされていない。引き続き専門家との連携も取りながら、指定難病への認定を要望していく。 - 医療費助成の25歳までの引き上げ
成人後、特に25歳までは収入が少ない期間であり、医療費負担が重くのしかかり、必要な治療の継続が困難になる恐れがある。当面の解決策として、少なくとも25歳まで医療費助成を延長することが現実的な対策である。適切な治療を継続できれば、合併症の予防につながり、国民医療費の削減にもつながる。
成人1型糖尿病患者への医療費助成制度が実現しない現状に鑑み、私たちは当事者団体として本部所在地の佐賀県において、日本IDDMネットワークが実施主体となり、2024年4月から佐賀県在住の25歳までの成人1型糖尿病患者への医療費助成を開始し、さらに2025年4月からは佐賀県在住の42歳までの妊娠準備期間から産後1年までの成人1型糖尿病女性患者まで医療費助成対象を拡大している。また、岡山では医療機関との連携(協定)により、当該医療機関を受診する25歳までの成人1型糖尿病患者への医療費助成を開始した。(https://japan-iddm.net/life-info/healthexpenditure_v2/)
しかしながら、地域によっては受けられる医療に格差があってはならず、全国一律の制度の実現が強く望まれる。よって、当面の対応策として1型糖尿病患者への医療費助成を25歳へ引き上げるよう引き続き要望していく。
・要望先:福岡資麿厚生労働大臣
・要望書:20歳以上の1型糖尿病患者への医療費助成についての要望
・提出日(最新):2025年6月30日
20歳未満の患者とその家族の支援について
現状
要望内容
異なる申請窓口となっている、特別児童扶養手当と小児慢性特定疾病の医療費助成の申請窓口一元化を求める。
進捗状況と今後の対応
- 2022年4月8日付で厚生労働省難病対策課および障害保健福祉部企画課から各都道府県・指定都市などに宛て、小慢の申請時に特児などの手当て制度の周知を求める事務連絡(https://japan-iddm.net/wp-content/uploads/pdf/220408_Jimurenraku.pdf)が発出された。
- 2025年3月の「障害保健福祉関係主管課長会議資料」の特別児童扶養手当の項目で、「特別児童扶養手当等の広報の充実について」として患者・家族による小慢の申請時には求めに応じて特児を案内するようにと明記された。
- 申請窓口の一元化については引き続き要望していく。
・要望先:福岡資麿厚生労働大臣
・要望書:特別児童扶養手当と小児慢性特定疾病の申請窓口の一元化についての要望
・提出日(最新):2025年6月30日
新たな医療技術、医薬品、医療機器の承認の迅速化と患者医療費負担軽減について
現状
要望内容
持続血糖測定器(CGM)やインスリンポンプの処方期間の延長、使用実態に合わせた処方点数の設定、緩徐進行1型糖尿病への対応拡大、臨床検査技師への対応拡大、処方する医療機関の拡大についてその対応を求める。
進捗状況と今後の対応
進捗がないので、引き続き要望していく。
・要望先:福岡資麿厚生労働大臣
・要望書:インスリンポンプおよび持続血糖測定器に係る診療報酬についての要望
・提出日(最新):2025年6月30日
・要望先:福岡資麿厚生労働大臣
・要望書:持続血糖測定器(CGM)に関わる診療報酬についての要望
・提出日(最新):2025年6月30日
医療に関する規制緩和について
現状
- インスリン補充の副作用である「重症低血糖」の対応について教育現場では、学校等の教職員等によるグルカゴン点鼻製剤(バクスミー®)の投与が緊急やむを得ない措置として実施可能となったが、救急救命士による投与は認められていない。
※詳細はこちら(https://japan-iddm.net/news/info/31072/)をご覧ください。 - 医療機器や医薬品関連企業から患者・家族への直接的な情報提供が厳しく制限されている。
要望内容
- インスリン補充療法を行っている糖尿病患者が重症低血糖を起こしている場合、救急救命士が緊急対応として、救急現場で点鼻粉末グルカゴン「バクスミー®」を使用することについて、医師法違反などの違法性が問われることのないよう通知発出等の対応をお願いする。
- 私たちのような一生病に付き合っていかなくてはならない患者・家族が、企業からの製品情報の提供や情報交換を行うことについて、特に阻害要因とされるのが「広告の該当性」3要件解釈の中の「顧客を誘引する意図」及び「一般人」の解釈である。患者・家族が必要な医薬品等の情報入手が可能になるよう、関連法令等の整備、関連通知の発出などの対応をお願いする。
進捗状況と今後の対応
- 「重症低血糖」についての教育現場と救命現場での対処
2020年10月 点鼻薬(粉末剤)のグルカゴン製剤(バクスミー®)が発売され、従来の注射薬に比べて格段に使用が容易になった。これに伴い、2020年度から要望を開始。 2024年1月 2024年1月25日付の文部科学省および子ども家庭庁から都道府県などへの事務連絡(【事務連絡】学校等における重症の低血糖発作時のグルカゴン点鼻粉末剤(バクスミー®)投与について.pdf)により、教職員等による本点鼻薬の使用が可能であることが示された。
一方で、救急救命士による使用は認められていないのでその点について要望を継続。2025年5月 2025年5月28日付の「規制改革推進に関する答申」で救急救命士による救命現場でのバクスミーの使用が規制改革の検討対象として明記された。
低血糖発作症例に対するグルカゴン粉末製剤の点鼻投与について、期限を設けた上で新たな救急救命処置の候補とするかの検討を行い、結論を得た上で速やかに必要な法令上の措置を講ずることとされている。本件の実現に向けて引き続き要望していく。
- 製薬企業・医療機器関連企業からの患者・家族に向けた情報提供
2024年2月に要望書を提出し、その後、同年3月18日の佐藤大作厚生労働省医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課長(当時)による業界団体への講演「医療用医薬品の販売情報提供活動に関するガイドライン―Q&Aその4について―」の中で、「広告の該当性に関し、医薬品等の適正使用推進や安定供給に係る情報の提供等、顧客を誘引する意図がない情報について自社製品と他社製品との比較の上で提供することは、広告には該当せず、これを行うことは差し支えない」と明確に示された。
しかしながら、企業側の理解が十分とは言えず当該企業との情報交換がスムーズに行えるよう引き続き要望していく。
・要望先:福岡資麿厚生労働大臣
・要望書:救急救命士の重症低血糖対応についての要望
・提出日(最新):2025年6月30日
・要望先:福岡資麿厚生労働大臣
・要望書:製薬企業・医療機器関連企業からの患者・家族に向けた情報提供についての要望
・提出日(最新):2025年6月30日
介護職員によるインスリン療法の実施について
現状
要望内容
介護施設に入所中のインスリン補充療法を行っている糖尿病患者や在宅療養中の糖尿病患者に対して、介護施設などの介護職員がインスリン療法を行うことについて、違法性が問われることのないよう関係法令の整備、通知発出等をお願いする。
進捗状況と今後の対応
| 2021年12月 | (公社)全国有料老人ホーム協会が2021年6月から8月にかけて行った全国の「有料老人ホーム」設置者へのアンケートによると、インスリン自己注射の困難な入居者に対しては退去を求め、インスリン自己注射の困難な入居希望者に対して入居を断ると回答した施設は全体の22%に上っている。その理由としては「看護師不在」、「ホームでは医療行為を行わない」などが挙げられている。 この結果を踏まえ、2021年12月に要望書を提出(以後、毎年要望)。 |
|---|---|
| 2024年6月 | 2024年6月21日に閣議決定された「規制改革実施計画」において、介護職員による医療行為について「一定の要件の下、介護職員が実施可能と考えられる行為の明確化についてその可否を含めて検討し、結論を得る。その上で、厚生労働省は、介護職員が実施可能とする行為があるとの結論を得た場合には、一定の要件の下、介護職員が実施可能とする行為の実現のために必要な法令、研修体系等について検討し、結論を得次第、速やかに必要な措置を講ずる。」とされた。 |
本件の実現に向けて引き続き要望していく。
・要望先:福岡資麿厚生労働大臣
・要望書:介護施設などでの介護職員によるインスリン療法の実施についての要望
・提出日(最新):2025年6月30日
糖尿病の障害年金「障害等級2級」認定基準について
現状
そのため残る選択肢は障害基礎年金の2級であるが、現在は糖尿病を対象とした障害等級2級の認定基準が明確に示されておらず、該当する患者・家族はその申請の検討にあたり、自らの療養状況などについての申請判断の材料がないに等しい状況にある。
要望内容
糖尿病患者が根拠を持って申請できるように、糖尿病についての「障害等級2級」の認定基準を明確に定めていただきたい。
経緯
2024年4月19日の大阪高等裁判所における、1型糖尿病患者8名の原告による障害年金の2級認定(不支給は不当)を求めた裁判では、原告勝訴となり、合併症を持たない1型糖尿病患者への障害年金2級の支給が認められた。この裁判例は1型糖尿病患者へ障害基礎年金2級が支給される可能性を示したことになるが、現在は障害等級3級のような具体的な認定要件は国からは示されておらず、認定基準の明確化を求めて今回初めて要望書を提出した。
・要望先:福岡資麿厚生労働大臣
・要望書:糖尿病の障害年金「障害等級2級」認定基準についての要望
・提出日(最新):2025年6月30日
お問い合わせ先
〒840-0854 佐賀県佐賀市八戸二丁目1番27-2号
認定特定非営利活動法人日本IDDMネットワーク
TEL:0952-20-2062 FAX:050-3385-8940
E-mail info@japan-iddm.net